助成決定団体
2024年度(令和6年度)の「環境市民活動助成」に、たくさんのご応募誠にありがとうございました。応募総数は425件となりました。
厳正な審査の結果、2024年度単年度として、268件に総額1億2,627万6,677円の助成が決定しました。これに、原則3年間助成するNPO基盤強化助成の2022年度、2023年度から継続する7団体を合わせ、2024年度の助成決定総数は275件、助成総額は1億5,392万6,505円となりました。
2001年度から2024年度までに、累計で5,178件、金額にして約30億3,269万3,353円の助成金を全国の環境市民団体にお届けし、地域活動を支援しています。
セブン-イレブン記念財団は、セブン-イレブン店頭の募金箱に寄せられた市民の皆様からの思いと、地域で活動されている市民の方々による環境市民活動とをつなぐ架け橋として、日本の環境市民活動を支援してまいりますので、今後とも皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
2024年度(令和6年度)助成の種類
| 助成の種類 | 助成の趣旨と特徴 |
|---|---|
| NPO基盤強化助成 | 地域の課題解決のために行う革新的かつ持続可能な自主事業の構築・確立をめざすNPO法人に対し、事業資金・専従職員の人件費・事務所家賃を原則3年間支援します。 |
| 活動助成 | 自然環境保護や生物多様性の保全、気候変動対策、体験型の環境学習など、市民が主体となって行う環境活動を1年間支援します。 |
| 地域美化助成 | ごみのない、緑と花咲く街並みをつくる活動を1年間支援します。 |
| 未来へつなごう助成 | 地域の環境課題解決のために活動する大学生・大学院生の取り組みを1年間支援します。 |
2024年度(令和6年度)助成決定
| 助成の種類 | 応 募 | 単年度の助成決定 | 複数年継続を含む 助成決定 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 申請金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| NPO基盤強化助成 | 30件 | 97,936,803円 | 3件 | 11,564,338円 | 10件 | 39,214,166円 |
| 活動助成 | 236件 | 158,135,733円 | 129件 | 75,334,873円 | 129件 | 75,334,873円 |
| 地域美化助成 | 148件 | 43,980,136円 | 127件 | 37,057,368円 | 127件 | 37,057,368円 |
| 未来へつなごう助成 | 11件 | 2,743,528円 | 9件 | 2,320,098円 | 9件 | 2,320,098円 |
| 合 計 | 425件 | 302,796,200円 | 268件 | 126,276,677円 | 275件 | 153,926,505円 |
2024年度(令和6年度)助成先一覧
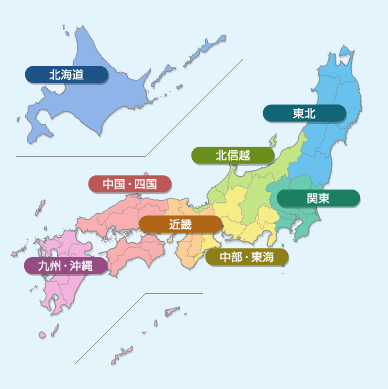
助成先団体選定は、透明性と公正性を高めるために、活動分野ごとに審査する専門審査会と、その結果をもって広い視点から審査を行う最終審査会の二審査制をとっています。原則3年間継続して支援するNPO基盤強化助成は、最終審査会においてプレゼンテーション審査を実施しています。
専門審査会審査員
| 活動分野 | 担当審査員 | ||
|---|---|---|---|
| 自然環境の 保護・保全 |
森林の保護・保全 | 宮本 至 | NPO法人 森づくりフォーラム 事務局長 |
| 里地里山の保全 | 竹田 純一 | 株式会社 森里川海生業研究所 共同代表 | |
| 里海の保全 | 木村 尚 | NPO法人 海辺つくり研究会 理事・事務局長 | |
| その他の自然環境 の保護・保全 |
横山 隆一 | 公益財団法人 日本自然保護協会 参与 | |
| 野生動植物種の保護・保全 | 吉田 正人 | 筑波大学大学院名誉教授 | |
| 総合環境学習活動 | 加藤 超大 | 公益社団法人 日本環境教育フォーラム 事務局長 | |
| 暮らしの中のエコ活動 | 崎田 裕子 | ジャーナリスト、環境カウンセラー | |
最終審査会審査員
| 川北 秀人 | IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者 |
| 佐々木 真二郎 | 環境省 大臣官房総合政策課 民間活動支援室長 |
| 入江 彰昭 | 東京農業大学教授 |
審査講評
今年度も多数のご応募をいただいたことに、深く感謝いたします。昨年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に位置付けられ、全国で多様な活動が再開されましたが、この数年間にも高齢化や人口減少はさらに進み、担い手不足はあらゆる分野で深刻化しています。このため当助成も次世代の育成を願って「未来へつなごう」助成を新設し、NPO基盤強化助成を拡充する意向で選考に臨みました。
活動助成にもNPO基盤強化助成にも共通するポイントは、環境・生態系や人々のくらしにおけるニーズ、課題解決や価値創出の手法の具体性、そして組織や地域に「残る」成果です。NPO基盤強化助成の審査では、組織の内外での人材育成や、情報開示やノウハウ活用による資金調達の拡充がどれだけ期待できるかが、大きな論点となりました。環境も活動も組織も、ともに持続可能性が高まるご提案を、次年度も楽しみにお待ちいたします。
最終審査会審査員 川北 秀人
(IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所] 代表者)